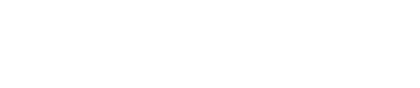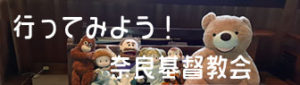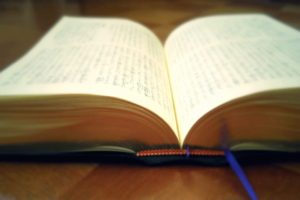「神さまの光をいっぱいにあびて」
YouTube動画はこちらから
ルカによる福音書13章1~9節
皆さま、お祈りをありがとうございました。先々週、フィリピンへ行ってまいりました。旅の目的は、アジア地域における聖公会の神学校会議に、ウイリアムス神学館の代表として出席することでしたが、それ以外にも、フィリピン聖公会第8代首座主教の着座式に参列し、さらに、私がチャプレンを務めている平安女学院中学高等学校と、現地の聖公会の高校との間に姉妹校協定を結ぶという大役も担わせていただきました。非常に濃密で充実した6日間でした。
会議の中心テーマは、脱植民地化を経験したアジアの国々において、「イエスの弟子として生きるとはどういうことか」を問うものでした。アジア独自の宣教神学を模索し、世界中の聖公会で共有されている「宣教の五つの指標」についても、アジアという文脈の中で改めて捉え直そうという試みがなされました。「アジア」と一言で言っても、その範囲は東の日本から西のパキスタンにまで及びました。それぞれの歴史や背景はまったく異なり、共通の認識を持つことは容易ではありません。しかし、それぞれの課題を分かち合いながら、まるで自国の問題であるかのように共に悩み、祈り合えるという恵みを実感しました。異なる国の仲間と深い連帯感を持てるというのは、本当に大きな喜びです。
聖公会の源流はイギリスにありますが、アジアに生きる私たちにとっては、地理的にも感覚的にも遠く感じられることがあります。それでも、共に集い、礼拝を捧げるとき、どの国の祈祷書であっても、大きな流れは共通しており、聖餐式を中心としたアングリカンの礼拝形式の中で心を一つにできるということに、大きな恵みを感じました。
さて、今日は大斎節第3主日、テーマはやはり「悔い改め」です。「悔い改め」と聞くと、どこか心が重くなる方もいらっしゃるかもしれません。「私はそんなに悪いことをしただろうか?」「悔い改めるような罪を本当に犯しただろうか?」そう思われる方もいるでしょう。
人を傷つけたことはあるか?盗みを働いたか?嘘をついたか?――もしかしたら、誰しも小さな嘘くらいはついたことがあるかもしれません。でも、それは誰かを思いやる「優しい嘘」だったかもしれません。私たちは本当に悔い改めが必要なほど罪深いのでしょうか? そう自問することがあります。
私たちは、日曜日に教会へ足を運び、祈り、聖書を読み、献金もする。イエス様を信じているのだから大丈夫、そう思ってしまいがちです。時として「信仰があるから災いは起こらない」と思い込み、何か悪いことが起こると「あの人に信仰がないからだ」「神に罪を犯したからだ」と、他人を裁いてしまうことがあるかもしれません。
けれども今日の福音書で、イエス様ははっきりとこう言われました。「災いは、その人の罪のせいではない」と。神さまは、災いをもって私たちを罰するような方ではありません。これは本当に、大きなグッドニュースです。
しかしその一方で、イエス様はこうもおっしゃいます。「もし悔い改めなければ、あなたがたも皆、同じように滅びる。」ここでの「滅びる」とは、単に肉体の死ではなく、永遠の命にあずかれない、つまり天の御国に入ることができないということを意味します。でも、私たちクリスチャンは、永遠の命を「死んだ後に与えられるもの」とだけ考えてはいません。イエス様を信じ、従って生きる今このときにも、すでに永遠の命に生かされているのだと信じています。
では、「悔い改める」とはどういうことでしょうか? 辞書には「過去の過ちを反省し、心がけを改めること」とありますが、聖書における悔い改めの意味はそれよりも深いものです。原語であるギリシャ語の「メタノイア」は、「180度の方向転換」を意味します。つまり、それはただ「ごめんなさい」という一瞬の行為ではなく、それまで神に背を向け、自分の思いや欲望で生きていた人生から、神の光の方へと完全に方向転換し、神と共に歩む新しい生き方への転換なのです。
そのように神の光を受けて生きるとは、どういうことでしょうか。私はふと、今回出会ったフィリピンの人々の顔が思い浮かびました。彼らは皆、本当に明るく、よく笑い、おおらかで、人生を楽しんでいるように見えました。もちろん、泣くことも怒ることも、時には悪態をつくこともあるでしょう。でも、それでもなお、あふれるような明るさを持っている――それは、どこから来ているのか。
それは「感謝」だと思うのです。自分が今、生かされているということ。神さまによって、周囲の人々によって支えられているということを、当たり前と思わず、感謝して生きている。その姿こそが、神を向いて生きている姿、悔い改めた生き方なのではないでしょうか。
聖書のたとえ話に戻りましょう。実を結ばないいちじくの木が、ぶどう園の中に1本だけ植えられています。周りには豊かに実を結ぶぶどうたち。取り残されたように実を結ばないいちじくの木が、うつむいて嘆いています。
そんな木に対して、主人は「切り倒せ」と言いますが、園丁は「どうか、もう一年待ってください。肥料を与え、手をかけてみます」と懇願します。この園丁こそ、私たちの主イエス・キリストです。イエス様は十字架にかかり、私たちの罪のために命を捧げてくださいました。その血と愛こそが、私たちを生かす「肥やし」となったのです。
この肥やしをしっかりと吸い上げ、神の光を受けて生きるとき、私たちはすでに悔い改めの道を歩み始めているのです。「神さま、ありがとう」と感謝を込めて両手を広げる――この姿勢こそが、悔い改めの証です。そのことをしっかりと心に刻みながら、イースターまでの4週間を、共に歩んでまいりましょう。