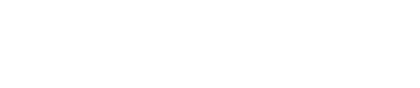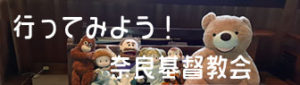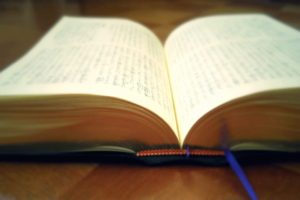「緑と平和、そして十字架」
YouTube動画はこちらから
ルカによる福音書9章18~24節
今日から教会暦の中では「聖霊降臨後の長い季節」、いわゆる「緑の季節」に入ります。11月の終わり、降臨節が始まるまで、しばらくこの緑色の時間が続きます。この「緑」という色、先週の説教では、「成長」また「命」を象徴すると言われていましたが、それだけではなく、緑は私たちの目や心を落ち着かせ、安らぎを与えてくれる、「平和」の色でもあります。
少し個人的な話になりますが、今から30年以上前、私がアメリカの大学で学んでいた頃、ある特別な出来事がありました。たまたまその大学に、裏千家の家元である千玄室さんが講演に来られたのです。私はそれまで茶道にはほとんど縁がなかったのですが、その日のお話の中で、彼が次のように語られたのです。「丸いお茶碗は小さな地球、小宇宙です。そしてその中にあるのは緑のお茶。それをいただくとき、私たちは地球に生かされていることを思い、自然と一体になり、そこに真の平和を感じてほしい」と。当時の私は茶道のことなんて何も知りませんでしたし、お茶の作法もさっぱりでしたけれど、その言葉は不思議と胸に残って、それ以来、お抹茶をいただくたびに、神さまの創造されたこの世界に生かされていること、そして「平和」というテーマが頭に浮かぶようになりました。
そして不思議なことに、後になって知ったのは、茶道とわたしたちが行っている聖餐式には多くの共通点があるということでした。千利休の時代には、キリスト教の宣教師たちが来日していて、彼らと利休との交流もあったそうです。千利休はキリシタンにはなりませんでしたが、ミサの影響を受けたであろうと言われています。そして反対に、宣教師たちも茶の湯の精神性やその簡素な美に心を打たれたといいます。文化も信仰も違う人々が、互いを尊敬し、学び合い、心を通わせる。それこそが、まさに「平和のはじまり」なのではないでしょうか。
さて、平和と言えば、明日6月23日は「沖縄慰霊の日」です。ご存知のとおり、沖縄戦が事実上終結したとされる日です。今年も奈良基督教会から、聖公会の平和の旅に参加されている方々がいらっしゃいます。そして今年は教会からも千羽鶴を、慰霊の日の礼拝に合わせてお送りしました。
そして今、私が身に着けているこの緑のストールは、2年前に天に召された東京教区の山野繁子司祭の形見です。山野先生は、日本聖公会で初めて女性司祭として按手された方で、私にとって本当に尊敬すべき大先輩です。
実は、彼女、今日奉献のときに歌う聖歌423番「沖縄の磯に」の作詞者なのです。平和の旅で沖縄を訪れた山野先生は、ある時、浜辺に小さな木の十字架を立てて、数人で静かに礼拝をされたそうです。その浜辺は、かつて血に染まり、市民が洞窟の中で集団自決を迫られた場所でした。その時の彼女の思いが、歌詞にそのまま現れています。「救いを求めて叫ぶ声に、主よ、あなたはどこにおられた?」この詩の問いは、神の沈黙に直面した人々の、深い絶望の叫びです。
そして、この沖縄の苦しみは、単なる「過去の戦争の話」ではありません。これは、私たちが今も背負っている、日本という国の十字架です。悲しいことに、この十字架は終わってはいないのです。米軍基地の問題、土地の問題、沖縄の人々が抱えている不条理な痛みは、「今も続く痛みのしるし」であり続けています。
でも、この聖歌はそこで終わりません。絶望で終わるのではなく、やがてそれが希望へとつながっていくのです。3節の最後にこう歌われます。「新しいいのち、生き抜くことへの励ましの言葉となる」。この言葉には、イエス様の十字架と同じ希望の光が込められています。イエス様の十字架も、ただの苦しみで終わりませんでした。その先に復活があり、永遠のいのちへの道が用意されていたからです。
沖縄の言葉で「命こそ宝」という意味の「ヌチドゥタカラ」が、この聖歌の折り返しに繰り返し出てきます。どんな命も、どんなに小さく、目立たなくても、それは神さまから与えられた大切な、大切な宝物なのです。
今日の福音書の中で、イエス様はこうおっしゃいました。「わたしについて来たい者は、自分を捨て、日々、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい。」とても厳しい言葉です。でも、そのあとにこうも言われました。「自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、わたしのために命を失う者は、それを救うのである。」
これは一見、矛盾しているように思える言葉かもしれません。でも、この言葉の本当の意味は、「本当に大切なものは、自分を守ることではなく、誰かのために生きること」だということなのではないでしょうか。私たちが、イエス様のあとについていこうとする時、自分の中の「小さな十字架」を背負わなければならないことがあります。それは、他の人には見えないものかもしれません。失敗、病気、孤独、家族の問題、将来への不安…。でも、それを背負って歩く時、私たちは決して一人ではないんです。イエス様も私たち一人ひとりのために十字架を背負われました。そしてその十字架の向こうに、復活の光があった。だからこそ、私たちも歩けるのです。
今年は終戦から80年の節目の年でもあります。けれど、世界では今も戦争が次から次へと起こり、人が苦しみ、命が軽んじられています。だからこそ、私たちは信仰によって、この世界に、十字架を背負いながらも、希望の光を灯す人になりたいのです。 祈り、歌い、歩むその一歩一歩が、平和の種となり、誰かの命を守ることにつながっていきますように。主の平和が、私たちのうちに、そしてこの世界に満ち溢れますように。