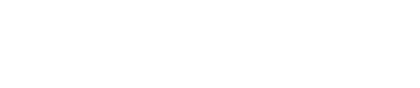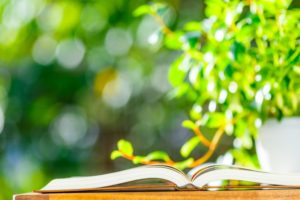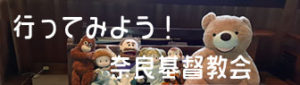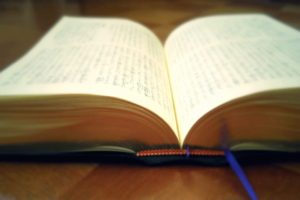「イエス様の栄光」
YouTube動画はこちらから
ルカによる福音書9章28~36節
さて、「栄光」ってどのようなイメージなのでしょうか。たとえば「栄光を手にする」という言い方がありますが、これを言い換えるならどのような言葉になるでしょうか。優勝する、制覇する、栄冠に輝く、そのような言葉が思い浮かぶと思います。そしてこれらの言葉に共通するのは、山を登り切ったというか、何かに到達したというか、そのようなことです。「勝利」という言葉にあらわされるように、何か光り輝くものを手に入れた、そういう感じなのかもしれません。でもだとすると、わたしたちの思い描く大斎とは、だいぶイメージが異なるようにも思います。大斎はどちらかというと、暗い中で静かに時を過ごす、そんな感じを持つことも多いからです。
山の上で祈っている中で現された栄光、そこにはペトロ、ヤコブ、ヨハネという三人の弟子たちがいました。イエス様の光り輝く栄光を見せられた彼らは、どのような思いでその光景を見ていたのでしょうか。「先生、わたしたちがここにいるのは、すばらしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリヤのためです」。ペトロが何も考えずに言ったこの言葉は、ペトロの本音をあらわしています。ペトロは思いました。イエス様、このままここにいてくださいと。仮小屋を建てるということは、そこに住んで欲しい、とどまって欲しいということです。山の上にずっといて、その場所で栄光を現して欲しいということです。
ペトロはなぜ、そのようなことを思ったのでしょうか。それは今日の箇所の直前、ルカ9章21節から27節の出来事が関係しています。そこには何が書かれているのか、それはイエス様がご自分の受難を予告した出来事です。「人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている」。イエス様はこのようにご自分の受難を予告されました。「人の子」、それはすなわちイエス様ご自身のことです。それが、「排斥されて殺される」、この言葉はペトロたち弟子にとっては驚くべきことだったはずです。
イエス様は、ご自分の死を予告されました。エルサレムに行くことは、死を意味しています。
「イエス様、もうここにいて下さい。山の上に建てる幕屋で、あなたの栄光を輝かせ続けて下さい。ふもとに降りることはありません。そこに待っているのは、あなたの死なのだから。そんなところに行く必要はないんです」。そのペトロの叫びは、イエス様を十字架の死から救いたいという思いもあったでしょう。そしてそれに加えて、自分の身を守りたいという思いもあったかもしれません。しかしその叫びを聞いても、イエス様はご自分の足を止めようとはされませんでした。
今日の箇所には書かれていない続きの部分には、このように書かれています。「翌日、一同が山を下りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた」。つまりイエス様は、ペトロ、ヤコブ、ヨハネという弟子たちを連れて、山から下りてしまったのです。
山を下りると、そこに待っているのは群衆です。傷つき、疲れ果て、救いを待ち望んでいる、というよりも救いにすがるしかない、そんな人々です。イエス様はそのような人たちの間に立たれたのです。
イエス様が山の上にとどまり、幕屋でずっと過ごしておられたら、イエス様の十字架はありませんでした。そもそもイエス様はなぜ十字架につけられなければならなかったのか、それはわたしたちの罪が赦され、わたしたちと神さまとが正しい関係に戻れるように、その架け橋として、罪の贖いのためにイエス様は血を流されたのです。その十字架の血によって、自分の罪と弱さに気づかされ、神さまの方に向き直った人物がいます。その人の名はパウロです。彼はもともとイエス様に従う人たちを迫害していました。キリスト者と呼ばれる人たちを、痛めつけていたのです。そのパウロが、復活のイエス様に出会って変えられました。回心しました。イエス様が人々の間で十字架に向かわれたから、神さまがそのようにご計画されたから、パウロの目は開かれ、福音を伝える人となったのです。パウロはイエス様の福音を伝えるために様々な場所に出掛け、教会を作ります。そしてその教会に宛てて、たくさんの手紙を書いていきました。聖書にはその手紙が収められています。その手紙を読むと、イエス様が山から下りて人々に伝えたかったことが、わたしたちの耳にも届いて来るのです。
今日読まれた使徒書の言葉は、コリントの信徒への手紙Ⅰ12章27節から13章13節です。「あなたがたはキリストの体であり、また、一人一人はその部分です」から始まるこの言葉は、わたしたちがイエス様の体として、イエス様と共に生かされていることを伝えてくれます。そして後半部分には、「愛」について書かれています。「愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない」。そして最後は、このような言葉で締めくくられています。「それゆえ、信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である」。
信仰と希望、それは山の上のイエス様との関係の中で培われるものかもしれません。信仰は自分自身が上の方に向かって、「イエス様、わたしは信じます。わたしはついて行きます」と宣言するようなものだと思います。そして希望は、一方的に与えられるもの。わたしたちが上を見上げて涙を流すときに、「あなたの祈りは聞かれたよ」と上の方から与えられるもの。それがわたしたちに対する希望かもしれません。
では、愛はどうでしょう。愛はまず、神さまから与えられます。そしてわたしたちはその愛の故に、互いに愛し合いなさいと促されます。言うなれば、愛がまずわたしたちの真ん中に「ドン」と落とされ、それをわたしたちは分かち合っている、そのようなことなのかもしれません。その「ドン」と真ん中に愛をもってこられたのが、イエス様なのです。彼は神さまの愛を伝えるために、山の上に留まろうとはされませんでした。イエス様が山を下り、わたしたちの真ん中に立ってくださったから、わたしたちには必要な愛があふれるほど与えられ、わたしたちも「愛する者」と変えられたのです。
愛はすべてにまさる大いなるもので、決して滅びない。その愛をわたしたちに与えるために十字架へと向かわれたイエス様。その歩みがまもなく始まっていきます。十字架への道を噛みしめながら、その愛を心に刻んでいきましょう。この水曜日から始まる大斎の期間が、皆さまにとって豊かな時間となりますよう、お祈りいたします。