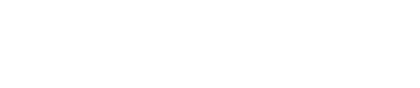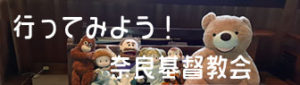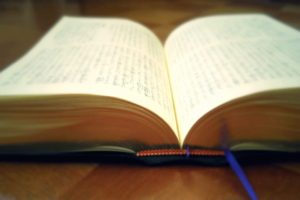「籠の中の恵み」
YouTube動画はこちらから
マルコによる福音書6章30~44節
弟子たちは多くの悪霊を追い出し、多くの病人をいやしてきました。そこでイエス様はその労をねぎらうという意味でしょうか、「あなたがただけで人里離れた所へ行って、しばらく休むがよい」と言われます。しかし群衆は弟子たちの後を追い、ついて来ました。そしてイエス様はその群衆の姿を見て深く憐れまれたというのが今日の箇所のスタートです。「飼い主のいない羊のような有様」、そのようにイエス様は自分たちの元に押し寄せる群衆を見ます。イエス様はその憐れみによって、時間を忘れて群衆たちに語り続けます。そのうちに日が傾いて来ます。そこは人里離れた寂しい場所、集まっていたのは5000人を超える人です。近くにそれだけの人数をまかなうお店もありません。
しかしイエス様は、「人々を解散させてください」と願う弟子に対して、「あなたがたが彼らに食べ物を与えなさい」と答えられます。そんな無茶な、200デナリオン、200万円分のパンがあったって足りないよ、と言う弟子たちの前で、今日の奇跡はおこります。弟子たちが持っていた5つのパンと2匹の魚が、弟子たちが配っていく中で、驚くことに5000人以上いた人たちを満腹させた。それが今日の福音書の物語です。でも今日は、その次に書かれたことについて、目を向けてみたいと思います。
今日の箇所の最後の方、43節にこのような言葉が書かれています。「そして、パンの屑と魚の残りを集めると、十二の籠にいっぱいになった。」
たった5つのパンと2匹の魚で5000人がお腹いっぱいになった、その出来事が強烈すぎて、どうしてもそちらにばかり目が行きがちですが、この「12の籠」って何なのか、そこを今日はご一緒に考えていきたいと思います。そもそも、パン屑と魚の残りって何でしょうか。確かにみんな満腹になりました。でもだからといって、「もうお腹いっぱいだしこれいらないや」って、持っていたパンを屑のように捨てるでしょうか。「魚、食べているけど、骨が多いからもういいか」ってポイしちゃうでしょうか。
当時のパンは、ナンのように平べったいものだったようです。ちぎって渡している間に、ちょっとずつ粉が落ちていった。それはあるかもしれません。でもそれが、12の籠いっぱいになるでしょうか。イエス様から預かった大切なパンです。それをそんな雑な配り方をするのであれば、弟子失格だと言われてもしょうがないでしょう。
現実的に、残り物や落ちた屑が、12の籠いっぱいになったというのは考えにくい。だとすればこの出来事には、違う意味があるのかもしれません。それこそがわたしたちに与えられたメッセージではないかと思うのです。
この前の木曜日、たまたまテレビを見ていましたら、SONGSという番組をやっていました。NHKの番組で、あるシンガーにスポットを当てて歌や話を聞いていく。そのようなものです。 その日のゲストは、ゆずでした。名前を聞いてもピンと来ない方もおられるかもしれません。アテネオリンピックのときに使われた「栄光の架橋」という歌や、朝ドラ「ごちそうさん」の主題歌「雨のち晴レルヤ」だったら知っている方もおられるでしょう。
番組ではこの4月にゆずの二人が、輪島高校を訪れた様子を紹介していました。輪島高校は能登半島に位置し、今年1月1日の能登半島地震で大きな被害を受けていました。そこに通う生徒の中にも避難生活を送っている人、家が傾いてしまった人など、そういう人たちの紹介もありました。その4月に学校の体育館でおこなわれたミニライブでは、様々なメッセージソングが歌われ、また生徒たちと一緒に大合唱が起こり、会場は笑顔と、涙と、感動に包まれたということでした。
でも番組は、それでは終わりませんでした。ミニライブがあった2か月後、6月に番組のスタッフだけが再び輪島高校を訪れます。その中である男子生徒の心境の変化が紹介されていました。その高校生の彼は元々料理人を目指しており、高校を卒業したら石川県を出て、県外で働きたいという思いを持っていたそうです。ところがそこに、心境の変化があった。料理人をやめようというのではありません。彼はこのように決断しました。「この輪島に残って、料理人を目指すんだ」と。どうしてそのような思いになったのでしょうか。彼は歌を通して、たくさんのエールを受け取りました。そして気づいたんですね。次は自分の番だと。自分が周りの人たちに、元気を届けたいと彼は思ったということです。
このSONGSというNHKの番組、明日月曜日の深夜11時50分から再放送されるそうです。かなり夜遅い時間ですが、もしご興味のある方は是非ご覧になってください。寝不足になっても責任は取れませんが。
話を福音書に戻しましょう。5000人の人たちは、自分たちが満腹になるほどのパンと魚をいただきました。でもそれは、「自分にちょうど良い量」ではなかったのです。手のひらいっぱいに広げても、あふれてしまう。食べても食べても、いつまでも減ることがない。
それは言い換えれば、神さまからのお恵みです。神さまはわたしたちに、受け止めることの出来ないほどの恵みを与えられます。腹八分目などとケチなことは言われません。いただいても、いただいても尽きない、豊かな水を湧き出たせる泉のように、いつまでもやまないスコールのように、神さまの恵みは尽きないのです。
弟子たちは見ました。その恵みがあふれ、こぼれ落ちている様子を。12の籠、それは弟子たちの人数と同じ数です。彼らはきっと一人一つずつ、あわてて籠を抱えていったのでしょう。そして溢れ落ちる恵みのパンと拾い集めていきました。それはそれぞれの籠一杯になりました。
さて、その籠一杯の恵みを、弟子たちはどうしたでしょうか。これは自分の分だって、どっかに隠してしまったでしょうか。そんなことはしなかったと思います。きっと、次に行った場所で、そこで出会った人たちと分かち合ったのではないでしょうか。 輪島の高校生が「次は自分の番だ」と決心したように、この恵みを次は誰と分かち合おうかとワクワクしながら、あふれ出る恵みをカゴに集めていった。その喜びにあふれた分かち合いの出来事が、宣教なのです。
わたしたちの目には、籠もパンも魚も、見えないかもしれません。でも神さまからの恵みは、間違いなくわたしたちの内に、そして周りにあふれています。その恵みをどのように用いていくのか。わたしたちが遣わされた場で、誰と分かち合っていくのか。
今日の礼拝後に教会では、宣教について語り合います。その中でまず、ご自分に与えられた恵みにも目を向けることができればと思います。わたしたちは与えられたから、与えることができるのです。そのことを心に留め、歩んでまいりましょう。