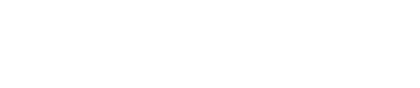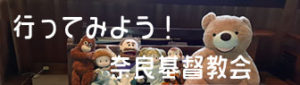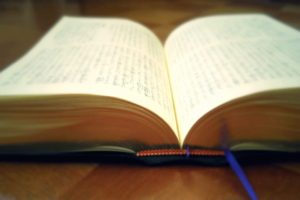「新しい夜明け」
YouTube動画はこちらから
ルカによる福音書21章25~31節
降臨節第1主日を迎えました。教会の暦では、新しい年の始まりとなります。紫の祭色が示すように、わたしたちが今、心に留めていくべきことは、暗がり、闇なのだろうなと思います。この暗さと静けさの中で光を待ち望む。暗闇の中でしか気づくことのできない光に目を向ける。そのような思いで降誕日を待ち望みたいと思います。しかしこの世界で生きていくと、なかなか光が見えてこないと感じることも多いのではないでしょうか。能登半島を始めとする自然災害。また世界では争いが続き、人が人の命を奪う日々が続いています。わたしたちの生活を見ても、毎日の中で孤独を感じたり、明日への希望を見失ったり、心の拠り所を求めたりします。これからクリスマスにかけて多くの人たちが教会を訪れるでしょう。その方々と共にわたしたちも、本当の光に気づくことができればと思います。
先週の火曜日、奈良県宗教者連帯会議主催の「平和の巡拝」というものがおこなわれました。奈良県宗教者連帯会議とはそもそも、部落差別やハンセン病問題など、「差別をなくす」という目的の元で宗教者が集まるということを目的にした団体です。
この団体にはキリスト教からはカトリック教会、日本基督教団、そして日本聖公会が参加しており、お寺や神社、また天理教などの新宗教など、27の団体が加盟しています。先日おこなわれたのは、その40周年の記念行事でした。
当日、当教会からもご一緒に歩かれる方、礼拝堂に来られる方を出迎える方、たくさんの方々のご協力を得ました。巡拝のルートは、浄教寺、奈良基督教会、興福寺、春日大社、東大寺です。それぞれ15名くらいの8グループが順次来られるようになっていました。わたしは礼拝堂で待機し、式文を使って短い礼拝をしました。その内容はというと、まず詩編を交唱し、次に主の祈りを唱え、さらにアシジのフランシスの平和を求める祈りを唱え、最後に「キリストの平和」を歌うというものでした。
朝日新聞の記事にも写真が載せられましたが、お坊さんたちが袈裟を着て、何の違和感もなくこの礼拝堂に静かに座っている姿には、とてもうれしい気持ちにさせられました。そして式文の主の祈りを、一緒に唱えてくれたんですね。みなさん独特の重低音で、「天におられるわたしたちの父よ」と唱えられたのが、とても印象的でした。
総勢120名以上の方々を順番にお迎えして、そしてわたしも一緒に行進に参加しました。興福寺、春日大社、東大寺、そして奈良県庁に進む道のりは、まあまあ大変でした。雨は降るし、人は多いし、なだら~かに坂になっている。しかしそれよりも何よりも、平和を願って一緒にお祈り出来たことが、とても心地よかったです。夕方に各宗派の代表者が集まって記念式典が催されましたが、その中でも多くの方々とこの経験を喜びあい、またこれからも祈りあいましょうとお話ししました。
キリスト教に限らず宗教というものは、人の心に光を与えていくものだと思います。そのアプローチの仕方は様々あるものの、暗闇の中でうずくまっている人に手を差し伸べ、光に導いていく。その思いは変わらないのだと確信できたわけです。
ただこういう話をすると、「牧師のくせに」とか「教会の礼拝堂にお坊さんを入れるなんて」という批判をされることがあります。でもそう考える方は、2000年前にイエス様が何をなさったのかということをもう一度思い起こしてほしいと思います。
2000年前、ユダヤでは当たり前のように、人を分け隔てしていました。自分たちは神さまに選ばれた民だと言い張り、この人たちは律法を守っていないから、この人たちは外国人だから、この人たちは病人だから、この人たちは女性だからと壁を作っていきました。それを今の世の中に照らし合わせると、「差別」という言葉になるのかもしれません。食事をする相手も限定し、会堂でお祈りする人も決めてしまい、様々な場面で人を排除していく人たち。それを見て、「そうではない、救いはすべての人に与えられる」と語ったのが、イエス様だったわけです。
2000年前、人々は光を待ち望んでいました。日々の苦しみから逃れられるように、希望をもって明日を生きることができるように、救い主が来られることを、今か今かと待ち望んでいました。それをご覧になり神さまは、わたしたちのためにイエス様をお与えになるという決断を下されます。ただイエス様は、ある特定の人たちが幸せになるような、ある決まったことを守る人たちだけが恵まれるような、そんな救い主ではありませんでした。
「主は地上をすべて治める王となられる。その日には、主は唯一の主となられ その御名は唯一の御名となる」。これは今日の旧約聖書、ゼカリヤ書14章9節に書かれたみ言葉です。
2000年前の人々は、「すべて治める王」とは、力ですべてを制圧する王様だと考えました。自分たちと敵対するローマ帝国などを滅ぼし、自分たちが住みやすい、自分たちにとって心地よい世界が訪れると信じていました。
しかしイエス様は確かに「王」として来られたかもしれませんが、徹底的に無力な王でした。その生涯の最後には着ている服をすべて脱がされ、当時もっとも残酷な処刑方法であった十字架の上で息を引き取りました。なぜそのような死を神さまは選ばれたのか、それはすべての人がイエス様の十字架の血によって罪を赦され、生きるようになるためです。旧約の時代、罪を犯した人たちは、自分の代わりに動物や鳥をいけにえにし、自分の代わりに血を流させました。その血によって神さまとの間の溝が埋められると思っていたからです。
しかしわたしたち人間は、そんなものでは足りないくらい神さまに背き、神さまの前に正しい者となることができませんでした。神さまはわたしたちとの間に大きく深くできてしまった溝を嘆き、イエス様の血によってその溝を埋めようとされたのです。そのイエス様の血は、わたしたちだけのものでしょうか。違います。わたしたちは自分の力でその血にあずかれる者となれたのでしょうか。それも違います。神さまはわたしたちを一方的に憐れんで下さり、ただただ愛するがゆえにわたしたちを含む、すべての人たちに命を与えてくださったのです。
だからわたしたちは、壁を作ってはいけないのです。せっかく神さまが壁を崩し、すべての人にみ手を伸べようとされているのに、その思いをないがしろにしてはいけないのです。
これからクリスマスに向けて、たくさんの方々が教会を訪れます。中には宗教が違う方、神さまのことを知らない方、いろんな方がおられるでしょう。しかしそれらの方々すべてを、神さまは愛しておられます。そのことを心から信じ、その人たちと共に歩むことができればと思います。そしてわたしたちの心にも、大きな光が与えられることを祈り、待ち望みましょう。よきクリスマスの準備ができますよう、お祈りを続けてまいります。