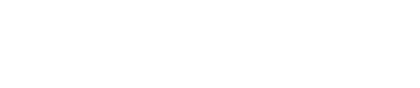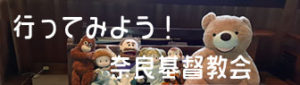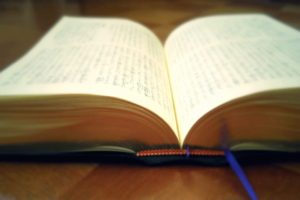「ぶどう園は誰のもの?」
YouTube動画はこちらから
ルカによる福音書20章9~19節
今回の箇所は、ぶどう園の主人が農夫にぶどう園を任せて出かけていった、そのような物語です。大地主が小作人に土地を貸し、その主人が収穫を得る代わりに、賃金か収穫の一部を労働者に渡す。よくある話です。このぶどう園の主人は収穫の時期を迎えたときに、当たり前のように収穫を渡すように農夫たちの元に人を遣わせます。しかしあろうことか、その申し出を農夫たちは断ってしまうのです。反乱です。自分たちが作ったぶどうだ。簡単に渡せるか。そういうことです。
この箇所を労働者の側に立って、解説する方がたまにおられます。「そんな、農夫に働かせるだけ働かせて搾取するなんて、ぶどう園の主人はひどい。これは農夫が反発して当たり前、資本主義社会の悪いところだ」って。でも果たしてそういうことでしょうか。イエス様が語られたのは、周りにいた民衆に対してでした。そして話が終わった後で、律法学者たちや祭司長たちはこのたとえが、自分たちに当てつけて語られたと気づきました。つまりこの農夫は、律法学者や祭司長、あなたたちのことだよ、ということです。では何が当てつけられたことなのでしょうか。イエス様はわたしたちに対して、一体何を伝えようとされているのでしょうか。今日はそのことをみなさんとご一緒に分かち合っていきたいと思います。
さて、今日の箇所はルカによる福音書20章です。イエス様はすでにエルサレムに入られていました。それから数日後に、イエス様は逮捕され、十字架につけられてしまいます。今日の物語は、その間に、イエス様が神殿の境内で教えられたものの一つです。イエス様はご自分がもう間もなく捕らえられ、十字架につけられることをご存じでした。イエス様はだから、弟子たちに、また民衆に、とても大事なことを、必ず伝えないといけないことを、熱心に語られたのでしょう。
旧約聖書を読んでいくと、神さまとイスラエルの人々が契約を結んだ場面が出てきます。それは、神さまがイスラエルの神となり,イスラエルが神の民となるという契約です。イスラエルの人たちは選ばれた民として、神さまのために働くというのがその趣旨です。つまり彼らは、任されたんですね。この世界を、神さまのみ心に適うものとすることを。だから彼らは一生懸命、力を尽くして神さまに仕えようとした。しかしその思いが、少しずつ違っていったのです。ファリサイ派、律法学者、祭司長、すべてこの時代のユダヤ教の中心にいた人たちです。彼らはわたしたちが思うよりもはるかに、敬虔で清い生活をしていました。神さまの掟である律法を忠実に守り、自分たちの思う正しさの中で生きていきました。そのために自分たちに対して汚れを持ち込みそうな人は、徹底的に排除していきました。自分たちだけのことを考えて、後は知らない。ぶどう園の農夫たちの中にも、そのような考え方があったのかもしれません。
しかしここで、少し違う角度からこの物語を見てみたいと思います。それは、この収穫されたぶどうは、一体最終的に、誰の元に行ったのだろうかということです。普通に考えたらぶどうはぶどう園の主人の元に行き、お金に変わっていくのでしょう。
しかしこのたとえは、イエス様が語られたものです。神さまのことをイエス様はたとえられているのです。だとしたら、これらのぶどうはぶどう園の主人が自分の財産を蓄えるために作ったものではないと思うのです。神さまだったらどうするか。きっとそのぶどうを、周りにいる人たちと分かち合ったと思うんです。
神さまはぶどう園というこの地に、わたしたち一人ひとりを遣わされました。その土地も、ぶどうの木も、自分のものではありません。自分の力で得たものではないのです。そして太陽の光も、雨を通して得られる水も、一緒です。すべて神さまから一方的にいただいたものです。神さまはわたしたちに、こう伝えられているのではないでしょうか。「あなたたちにはたくさんの恵みをあげよう」と。そしてそれを使って豊かな実を結び、周りにいる多くの人たちと分かち合って欲しいと願われたのです。
しかしわたしたちは、なかなかそれが出来ないんですね。お金を稼いだらそれは自分の力で得たもの、地位も名誉も、仕事も家族も、すべて自分のものなんだ。誰にも渡さない。そういう気持ちの中でわたしたちが歩むとき、それはきっと神さまが遣わした、収穫をもらいに来た人を追い払う、そのことと何ら変わらないような気がするんです。
来週教会では、宣教の呼びかけシリーズの第4回目をおこないます。おととしにおこなわれた宣教協議会の分かち合いです。今回は「人々の声に耳を傾けよう」というテーマで、開かれた教会について語り合っていきます。この宣教協議会からの呼びかけですが、3つの大きなタイトルすべて、「耳を傾けよう」という呼びかけになっています。「宣教」というとわたしたちは、何か拡声器を持ったりビラを配ったりして、自分たちの思いを一方的に伝えるもの、そのように感じるかもしれません。
しかしイエス様が示された宣教は、実はそうではありません。自分の考えを押し付けたり、自分の正しさを証明したり、そういうことではなくて、今、悲しんでいる人のそばにいる。今、苦しんでいる人の声を聞く。そういうことが大切なのです。
ぶどう畑の農夫たちは、その恵みを自分たちだけのものにしようとしました。最初の僕を袋叩きにして追い返し、次の僕も袋叩きにした上に侮辱して、何も持たせないで追い返してしまいました。三人目の僕は傷を負わされ、放り出されてしまいました。
ぶどう園の主人は、三人の僕がそんな目にあっても、強硬手段に出ることはありませんでした。本当であれば、一人目で怒りの行動に出てもおかしくありません。しかし彼は最後に、愛する息子をぶどう園に送るのです。
このぶどう園の主人は、神さまのことでしょう。神さまは、これらの恵みは、すべての人に与えられているのだ、ということを示すために、何度裏切られても、悲しい目にあっても、何度も何度もわたしたちに関わろうとされるのです。
最後に遣わされた愛する息子、イエス様は十字架へと向かわされます。本当であれば、それで物語は終わりです。しかし神さまは、そこで終わるのを良しとはされませんでした。十字架の血によって、イエス様は隅の親石となってわたしたち一人ひとりを支え、生かしてくださるのです。わたしたちには神さまから、たくさんの恵みが与えられています。それぞれの方に違った賜物も与えられています。わたしたちはそれを、誰と、どのように分かち合うのか。それが宣教であり、それがぶどう園の農夫に求められたことなのです。
ギュッと握りしめた自分のこぶしの力を少し抜いて、神さまにお委ねしていく。そのことを意識しながらイエス様の十字架と復活のときを迎えることができればと思います。